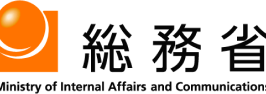総務省の支援事業
実証事業
先進無線タイプ
ローカル5Gをはじめとする新しい無線技術を活用した、地域の課題解決に向けた先進的な実証事業を支援します。ローカル5GやWi-Fi HaLowといった新しい無線技術を使うことに加え、①全国の各地域が共通で抱えている課題解決に役立つ先進的なソリューション②人材不足に起因する課題の解決につながる、地場企業の事業活動の効率化・合理化に役立つ先進的なソリューション――のどちらかに該当する実用化に向けた実証事業が対象です。
・全体予算
18億円程度
・実施主体
地方公共団体、企業・団体など
・対象となる無線技術
ローカル5G、Wi-Fi HaLow、Wi-Fi 6E/7などのワイヤレス無線技術
※他の無線技術については個別相談。
・実施形態
請負(定額)
※ネットワーク・ソリューション機器など、消耗品以外はリース経費のみ。リースがないものは購入できますが、事前に総務省の了解が必要。免許取得関係経費なども対象外。
・事業規模の目安
1,000万~1億円程度
活用のポイント
先進無線タイプを利用するにあたってのポイントやアドバイスをご紹介いたします。

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 デジタル経済推進室 課長補佐
佐藤 厚雄
さとう あつお
「ローカル5G」「Wi-Fi HaLow」といった新しい無線技術と、先進的なソリューションを組み合わせた実証事業が対象になります。たとえば、「人手不足」といった地域社会の課題に対して、新しい無線技術を使い、新しい技術・観点を導入した自動運転トラクターを試…

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 デジタル経済推進室 課長補佐
佐藤 厚雄
さとう あつお
活用のポイント
「ローカル5G」「Wi-Fi HaLow」といった新しい無線技術と、先進的なソリューションを組み合わせた実証事業が対象になります。たとえば、「人手不足」といった地域社会の課題に対して、新しい無線技術を使い、新しい技術・観点を導入した自動運転トラクターを試みるケースなどです。新しい無線技術を試すわけですから、現実世界で想定通りに動くかどうかは分かりません。失敗のリスクも踏まえ、全額補助となっており、地方公共団体だけでなく、地域社会DXに取り組む企業も費用の負担なく実証できます。
採択にあたっては、①地域課題が的確でソリューションと整合性がとれているか②社会実装や他地域への横展開に向けた具体的かつ現実的なビジョンがあるか――などを評価しています。2024年度までは、スタートアップの参加や「デジ活」中山間地域に登録されているかなどを加点評価していましたが、2025年度事業では、より実装・横展開を意識して①地域ICT企業が参加しているか②幅広い地域での共同利用を促すソリューションか――なども評価項目として加えました。地元企業の参加が、持続性のある仕組みを作るうえで重要であること、また横展開できない取り組みは高額になりビジネスモデルになりにくいことを踏まえた変更です。
技術ありきの提案ではなく、地域課題を出発点にしているかについては特に重要視しており、利用者の声やアンケート調査といった具体的なデータを用いて課題を説明している団体は的確だと判断されやすいです。次の実装への道筋についても、地方公共団体などの何らかの計画に則っていると説明されているような企画書は評価が高い傾向にあります。横展開に関しては、ソリューションのビジネスモデル、販売体制や資金調達体制に加え、地元のステークホルダーが参加したり、他地域でのニーズなどの聞き取り調査などが示されたりしていると蓋然性があると評価されやすいです。
1件あたりの事業規模は、2024年度までと同じ1,000万~1億円程度ですが、全体予算が1.5億増の18億円になり、より多くの地方公共団体や企業などが利用できるようになりました。
対象となる新しい無線技術は、衛星インターネット「Starlink」も対象ですし、ドローン利用向けの5GHz帯の屋外利用といった近年制度改正される既存の無線技術も対象です。地域課題解決に向けた新しいアイデアがある場合は、ぜひチャレンジしてください。
AI検証タイプ
携帯電話などに使われているLTEをはじめとする無線技術を有効に活用するため、AIを用いた通信負荷の低減・通信料の確保等に関して検証します。例えば、端末にAI機能を搭載した「エッジAI」を活用することで、端末からサーバーに送る通信量を抑えるほか、AI制御によって基地局からの電波に指向性を持たせ、端末を狙い撃つことで、多数の端末とのスムーズな大容量通信や、山奥や海中での通信を可能にする実証が想定されます。こうした技術を活用すれば、既存の通信技術の活用でも、様々な地域課題をより低コストで解決することが期待できます。
・全体予算
5億円程度
・実施主体
地方公共団体、企業・団体など
・事業規模の目安
上限1億円程度
活用のポイント
AI検証タイプを利用するにあたってのポイントやアドバイスをご紹介いたします。

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 課長補佐
小土井 一洋
こどい かずひろ
携帯電話網などの既存の通信技術を有効活用することで、より多くの地域課題を低コストで解決できるようになることを目指し、AIを使って通信の効率化を図るといった技術を実証する事業です。未来のデジタル社会を支える土台となる技術創出を目指しています。
…

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 課長補佐
小土井 一洋
こどい かずひろ
活用のポイント
携帯電話網などの既存の通信技術を有効活用することで、より多くの地域課題を低コストで解決できるようになることを目指し、AIを使って通信の効率化を図るといった技術を実証する事業です。未来のデジタル社会を支える土台となる技術創出を目指しています。
たとえば、通信が届きにくい海中で取得したデータをエッジAIで処理することで通信量を抑え、安定して通信を海上・地上に送るなどの試みが想定されます。AI制御によって基地局からの電波に指向性を持たせ、端末を狙い撃つことで、スムーズで大容量の通信を可能にする試みもあるでしょう。
高度な技術実証になるため、事業の中心は企業や大学になると思いますが、この技術をどのように地域の課題解決につなげていくのかという視点も重要になります。
AI検証タイプの実証事業は、2025年度から新しく始める事業になります。ただ、研究自体は企業や大学などですでに始まっていると思いますので、今回の事業については、その研究と地域課題とを結びつける大きなチャンスととらえてほしいと考えています。実証に関する経費は国が全額支援する形になるので、研究の種(シーズ)を持っている企業や団体がありましたら、この機会にぜひ挑戦してください。
自動運転レベル4検証タイプ
政府が掲げるデジタル田園都市国家構想の実現に向けて、「地域限定型の無人自動運転移動サービス(限定地域 レベル4)」の実装・横展開に当たって課題となる安全な自動運転に必要な通信システムの信頼性確保などに関する検証を実施します。レベル4の自動運転では、遠隔監視の実施などに当たり、通信の信頼性確保が必要です。交差点における通信や基地局間の切り替え、通信帯域幅の確保など、様々な検証項目が想定されます。安全な自動運転の早期実現により、渋滞につながる運転の抑止や高齢者の移動手段確保など、様々な地域課題の解決が期待できます。
・全体予算
22億円程度
・実施主体
地方公共団体、企業・団体など
※地方公共団体を1以上含むコンソーシアムを形成していることが要件となります。
・事業規模の目安
上限2.5億円程度
※車両費は補助の対象外です。
活用のポイント
自動運転レベル4検証タイプを利用するにあたってのポイントやアドバイスをご紹介いたします。

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 課長補佐
小土井 一洋
こどい かずひろ
政府では、デジタル田園都市国家構想総合戦略において「2027年度までに100か所以上 」で地域限定型の無人自動運転移動サービスを実現するという目標を掲げています。政府全体で連携して目標達成に向けて取り組んでいるところであり、その一環として、総務省としても…

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 課長補佐
小土井 一洋
こどい かずひろ
活用のポイント
政府では、デジタル田園都市国家構想総合戦略において「2027年度までに100か所以上 」で地域限定型の無人自動運転移動サービスを実現するという目標を掲げています。政府全体で連携して目標達成に向けて取り組んでいるところであり、その一環として、総務省としても引き続き自動運転レベル4検証に取り組んでいきます。
様々な地域で自動運転が取り組まれていますが、これまでの取り組みで課題も見えてきました。電波の届きにくい地域やトンネル内などでの安全走行をどう担保するか、また気候条件など運転環境が変わることでどのような影響がでるかといったこともその一例だと考えています。過去の取り組みで浮上した課題を抽出・整理して、それを乗り越えるための挑戦をしてもらいたいと思います。
とはいえ、課題を縛るつもりはありません。過去の取り組みで浮上した課題だけでなく、「こんな新たな課題が考えられる」というような提案も歓迎します。
自動運転については、今後、自動運転に取り組みたいと考える地域の皆様が参考になるような「モデル集」を作成したいと思っています。ですので、過去の実証事業と同じような課題ではなく、より新しい、もしくは難易度の高い課題に挑み、次のステップに進めるような事業を選定したいと考えています。
選定にあたっては①地域にとっての必要性や緊急性があるか②課題の新規性・難易度③実証できる体制が構築できているか――といった点について重点的に評価します。新規性は必要ですが、必ずしも技術的に高度な試みである必要はありません。実装を見据えたうえで、地域において自動運転を走らせるために解決が必要な課題に関する実証であれば、その技術的なハードルを乗り越える支援をしたいと考えています。
山間地域はもちろん、住民の移動手段の確保に困っている地方公共団体は多いと思います。取り組みを前に進めるような提案をお待ちしています。