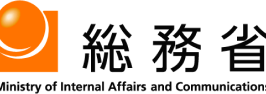共通の悩み抱える農山漁村へ、ICTで解決の糸口を
国内の第一次産業を支える農山漁村では、人口減少と高齢化が進行し、担い手不足による様々な課題に直面しているところが少なくありません。こうした課題について、宮城県はICT(情報通信技術)を解決の糸口にしようと、県内の農山漁村地域におけるICT活用を支援しています。「みやぎ農山漁村デジタルトランスフォーメーション推進事業」もその一環で、宮城県が農山漁村地域の市町村を対象に住民の声をふまえてDX推進による課題解決に向けた計画づくりなどを支援しました。地域のありたい姿を掲げ、到達までの道筋を示すことで、だれもが住みたくなる農山漁村の実現を目指しています。
県内で人口最少の七ヶ宿町をモデル地区に
「10年後、どんな町にしていきたいですか」。宮城県七ヶ宿町(しちかしゅくまち)庁舎の会議室。2021年12月、みやぎ農山漁村デジタルトランスフォーメーション推進事業のワークショップで、集まった各地区の住民や猟友会のメンバーら約20人にそんな質問が投げかけられました。宮城県南西部の中山間地域に位置する七ヶ宿町は2021年度にみやぎ農山漁村デジタルトランスフォーメーション推進事業のモデル地区に選ばれました。七ヶ宿町の人口は1,213人(2024年12月末)と県内で最も少なく、高齢化率は45.1%と宮城県内で最も高くなっています。

「この町で農業を続けていくためには、町全体で鳥獣被害対策にしっかりと取り組まなくてはならない」。ワークショップでは、迅速に解決したい課題として各世代とも鳥獣被害をあげている現状が浮き彫りになり、まずは町全体で対策を実施することで意見が一致。それを踏まえて、ICT機器を使って有害鳥獣の捕獲活動の効率化を図り、次のステップとして住民参加による鳥獣行動の情報共有と分析に取り組んでいくことになりました。七ヶ宿町農林建設課の三上広信課長補佐は、「大規模農家だけでなく家庭菜園を楽しんでいる住民の方々を含めて、みなさんが鳥獣被害対策を重要課題ととらえていることがわかりました。地域全体で課題を共有でき、力を合わせて取り組んでいこうという機運が高まることも実感しました」と語ります。

ICTで獣害対策に効果、関係人口の増加も
七ヶ宿町の基幹産業である農業では、蔵王連峰の清らかな水で育てた「七ヶ宿源流米」など稲作を中心にソバや野菜の栽培がさかんですが、近年、ニホンザルやイノシシによる食害被害が深刻化しています。ニホンザルの生息数が増加しているほか、イノシシも2010年に初めて確認されて以降、生息数が増えているためです。農作物の被害額は、ピーク時の2019年にはニホンザルによるものが137万円、イノシシは397万円に上りました。
七ヶ宿町が取り組んだのが、ICTを活用したおりワナ(捕獲機器)システムの導入です。システムを構成するICT機器を結ぶ通信網として、中山間地域で安定して長距離通信ができる広域無線ネットワーク「LPWA」を整備しました。町内におりワナの通信用のLPWA中継機3基を設置し、町内全域をカバーする通信網を形成したのです。
おりワナシステムは、ワナの部分が作動すると、設置されたセンサーが動きを検知し、担当者のスマートフォンなどにメールで通知する機能を持っています。町内6か所のワナにこのシステムを導入しました。
これまでは、有害鳥獣であるイノシシやニホンザルを捕獲する場合、担当者がすべてのワナを順番に見回っていましたが、通知のあったワナを優先するなどして作業の効率化を図ることができたといいます。このほか、町内の有害鳥獣の通り道などにセンサーカメラを設置し、ワナにどんな動物がかかったのか、誤作動だったのかなどの確認をすることもできるようにしました。

こうしたICT機器の導入のイニシャルコストは、センサーカメラが68万400円、通信網の構築を含めたおりワナシステムが348万2,160円。ランニングコストはセンサーカメラが年間3万6,960円、おりワナが年間19万9,520円です。このほか、鳥獣被害対策に関わるデータの見える化を進めました。七ヶ宿町の庁舎にRTK基地局を設置し、高精度な位置情報を把握できるようになり農業のスマート化に活用しています。また、ドローンを使ったニホンザルの生息状況の調査が可能となり、住民が協力して、ニホンザルの出現する位置をピンポイントで把握し、花火などを使った効果的な追い払いを実施できる体制が整いました。
七ヶ宿町では増加傾向が続いていた鳥獣被害額が2023年度には減少に転じるなど、ICT活用による効果が見えてきました。三上さんは「マンパワーが少なくてもICT機器を使いこなすことで、鳥獣被害を減らすという成果につながることが分かりました」と手ごたえを語ります。
七ヶ宿町ではいま、移住や関係人口の拡大を目指し、鳥獣被害対策も含めた様々な分野で町外との交流施策を進めています。例えば、2017 年から 2019 年までの3年間は、「いのししバスターズ」として町内外のボランティアを募り、ワイヤーメッシュと電気柵を複合させた「おじろ用心棒」を町内に農地のほぼ全域に設置する交流活動を行いました。そうした関係人口を増やす取り組みにより、移住・定住を希望する人が少しずつ増えています。1985年度から1990年度の5年間で約7.4%上昇していた高齢化率は、若い世代の移住が増えたことで2015年度から2020年度の5年間では、上昇が1%以下までおさえられています。 今後も関係人口の増加を目指し、VR(仮想現実) 上で町の景色を楽しみながら鳥獣の狩猟を体験してもらうなど、鳥獣被害対策にからめて町への関心を高めることも検討しています。三上さんは、「こうした計画をすべて実現できれば、町にかかわりたい、住みたいという人がもっと増えるのではないか」と期待を寄せます。
「住みたくなる農山漁村」の優良モデル構築へ
七ヶ宿町がモデル地区となったみやぎ農山漁村デジタルトランスフォーメーション推進事業では2021年度のスタートから2023年度までの実施期間で、同町以外にも加美町、大郷町、山元町、涌谷町をモデル地区に選定してきました。「誰でもできる農業」 「住みたくなる(住みやすい)農山漁村」を掲げ、宮城県が各町の農山漁村DX地域戦略計画の策定を支援しています。専門家を派遣し、県の担当者が伴走支援する形で行い、宮城県が内閣府の地方創生推進交付金(現・デジタル田園都市国家構想交付金)を活用し、約半額の補助を受けています。またICT機器の導入など計画の実現にあたっては、宮城県が国や県などの補助制度を紹介しています。七ヶ宿町は、おりワナシステムの導入にあたっては、農林水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して費用の全額を賄いました。

宮城県農山漁村なりわい課の中山間振興班技術主査の佐藤拓海さんは、「少子高齢化をはじめ、どの地域も同じような課題を抱えています。モデル地区を選定し、DX推進を支援することでその解決を図り、優良モデルとして県内に広めていく狙いがあります」と言います。
「DXは小規模の地方公共団体ほど効果があると思う」
その取り組みの方向性を定める地域課題の抽出にあたっては、将来のありたい姿を明確かつ丁寧に描くことから着手。各地でワークショップを作り、様々な立場の住民の声をもとに10年後になりたい姿、目標を決めてステップを考えるという手法で取り組みを進めてきました。佐藤さんもワークショップに立ち合い計画策定に関わるなか、「住民の方々の声は計画をつくる重要な要素になりました。農山漁村地域の課題の深刻さ、担い手がいなくて大変だということを実感すると同時に、改めてDX推進の必要性を感じました」と話しています。

宮城県農山漁村なりわい課の中山間振興班技術補佐の氏家俊幸さんも、「農山漁村地域が単独でDXを推進するのは、人や予算の余裕やノウハウがなく、きっかけがなければ難しい。そこで、県が足りない部分を補い、計画策定から支援することで取り組みを進めていくことができると考えています」と意義を説明します。そのうえで「中山間地域は、高齢化と人口減少が同時に進んでおり、いかに効率的に物事を進めるかが大切です。ICT機器の活用をはじめとするDXの推進は、規模の小さい地方公共団体ほど取り入れることで効果があると思うので、県内の課題解決に向けて、いろいろな形で支援を続けていきたいと考えています」としています。