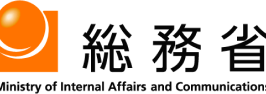村人口1,800人、高齢化率59% 生活の足確保
秋田県のほぼ中央に位置する上小阿仁村は、「天然秋田杉の里」として知られ、総面積(256.72㎢)の92.7%が広大な山林原野で占められています。人口は1,800人弱(2024年7月現在)。住民の多くは農林業に携わっていますが、高齢化が進み、65歳以上が占める割合は県内で最も高い59%となっています。1年の3分の1が雪で覆われる豪雪地で住民の移動手段の確保は大きな課題ですが、村内の集落間をつなぐ路線バスはなく、スーパーマーケットがある隣の市町と村とを結ぶバスの減便も続いています。こうした事情を背景に、村では全国に先駆け、自動運転サービス「こあにカー」の実証実験に取り組んできました。2024年には、総務省の「地域デジタル基盤活用推進事業」に採択され、ローカル5Gなどを活用したスムーズな運行監視に挑み、2024年12月17日に関係者を集めた視察会も開催しました。目指すのは、特定の条件を満たす限定された走行ルートにおいて、ドライバーが不要な「レベル4」の自動運転です。

ゴルフカート方式で「レベル2」の公道自動走行
「通常の走行中にハンドル操作は必要ありません。路上駐車や人を避ける場合は、ドライバーが手動に切り替えてハンドル操作します」 電動カートタイプの自動運転車両「こあにカー」の車上。視察会でドライバーを務めた「NPO法人上小阿仁村移送サービス協会」の萩野芳紀代表は、運行を見守りつつ、ハンドルから手を離してそう説明します。その様子は、村中心部にある道の駅に設けられた「遠隔監視室」にリアルタイムで送られ、路上の安全状況を遠隔で確かめられます。 車両が動く仕組みは、ゴルフカートなどに使われている「電磁誘導方式」です。道路に敷設された「電磁誘導線」から出る磁力を、車両のセンサーが感知し、誘導線上を時速12kmで自動走行する仕組みです。交差点など停止が必要な場所には、タグと呼ばれるマグネットが道路内に埋め込まれていて、これを車両のセンサーが感知して自動停止。動き出す際には、ドライバーが安全を確認して再起動ボタンを押して走行を再開させます。最大20cmほど積もった雪の上でも走行できるといい、レベル2と呼ばれる部分的な自動運転を実現しています。


2019年に全国初の社会実装、雪道も実証

「80歳を過ぎても元気で、移動もまだ自力でできるという住民は少なくありません。ですが、そういう人がさらに高齢化する近い将来、公共交通のニーズが一気に高まることが予想されています」
同村総務課の加藤浩二課長は、自動運転に取り組む背景についてそう説明します。
上小阿仁村が自動運転サービスに取り組みはじめたのは、2017年。内閣府のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)の自動運転実証実験に公募し、中山間、かつ豪雪地という気候条件から採択されたのがきっかけでした。村、NPO法人上小阿仁村移送サービス協会、「日本工営株式会社」などが協力して電動カートを使った自動運転を期間限定で試みた後、2019年11月、1回200円の運賃を徴収する形で、中山間地としては全国初となる自動運転サービスを社会実装しました。以降、SIPや国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業」の支援を受けて村内を巡回するルートを増やしつつ、雪道や道路の凍結といった課題を克服しながら運行を試みてきたといいます。
タクシー会社がない村内でライドシェアに取り組んできたNPO法人上小阿仁村移送サービス協会の人たちが、交代でドライバーを務めていますが、高齢化で担い手も減っています。「サービスを維持するには、できる限り人手や負担を省き、完全な自動運転に近づけていくことが重要なのです」と、萩野さんは指摘します。
ローカル5G活用し遠隔の安全監視に成功
そこで、自動運転レベル4につながる技術開発の一環として、2023年度から取り組み始めたのが、「安全監視」の遠隔化でした。「株式会社秋田ケーブルテレビ」と協力し、車体の前後左右などに計8台のカメラを設置。その映像を離れた場所からリアルタイムに確認し、安全運行に必要な情報を遠隔で得られるかを調べたのです。映像の送信には、携帯電話に使われている「LTE」という通信規格を利用。携帯などに使われるSIM4個を束ねるLTEボンディングと呼ばれる方式を用い、カメラ8台の映像をスムーズに送信できる通信量を確保。これを実証で試したところ、山の陰になるなどして通信状態が悪い場所では、映像が遅延するという課題が浮上したのだといいます。

2024年度は、総務省の「地域デジタル基盤活用推進事業」を活用し、その課題解決に挑みました。通信状態が悪い場所に大容量の通信が可能なローカル5Gの基地局を設置。LTEとローカル5Gとを切り替えながらスムーズな映像送信ができるかを試みたのです。その結果、走行ルート上で映像を遅延なくリアルタイムで送信することに成功。「完全自動運転に向けて、遅延のない遠隔監視は欠かせない技術。その第一歩をクリアできた」と株式会社秋田ケーブルテレビテクニカルクリエイト本部の湊忠親副本部長は語ります。
また、ローカル5Gを有効活用するため、岩手県立大学の柴田義孝名誉教授らと協力し、温度など各種センサーや路面を調べるカメラも車両に搭載。凍結や積雪、でこぼこなど路面状態を自動判定するシステムも構築しました。将来は集めたデータをAIに学習させ、気象条件から道路状態を予測して自動運転速度の調節などに役立てる試みにも挑戦したいといいます。

利用者増とコスト減が課題、 「レベル4」へ期待
サービスを維持し、レベル4の自動運転実装を目指すにあたり、課題は利用者数を増やすことと、コストの削減だといいます。「自分で車を運転できなくなったら利用したい」との声は多いのですが、人手不足のために予約方式で運行しており、巡回ルートもまだ限られているため、利用者数は高齢の女性を中心に月10人弱ほど。「今年から人口の多い集落への巡回も始まったので、料金の見直しや定期運行実施なども含め、利用者の掘り起こしを図りたい」と、自らドライバーも務めるNPO法人上小阿仁村移送サービス協会コーディネーターの長井直人さんは言います。

また、ランニングコストについては、電気代やメンテナンス費用だけであれば年70~80万円ほどですが、これにドライバーの人件費が加わります。完全自動運転に近づけることができれば、この人件費を削れる可能性もあり、その技術開発には大きな期待がかかっています。「運賃だけでコストをまかなうのは難しいですが、過疎化が進む地域の公共交通というセーフティネットをどう考えればよいのか。他の地域とも連携するなどして、解決策を見いだしていきたい」と、加藤さん。
湊さんも「今回の遠隔監視の成功を踏まえ、次は遠隔操縦へと、完全自動運転に向けたステップを着実に進めていきたい。また、ローカル5Gなど新しい通信規格を活用した他のDXも組みあわせるなど、様々な工夫を考えていきたいと思います」と話しています。