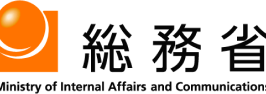紀伊半島の中央部に位置する奈良県天川村は、近畿最高峰の八経ヶ岳(1,915m)をはじめとする標高1,000~2,000mの「近畿の屋根」大峯山系の山々に囲まれた村です。人口は1,195人(2025年1月末時点)。村の総面積約175㎢のうち97%を森林が占め、4分の1は「吉野熊野国立公園」に含まれます。およそ1,300年前に役行者(えんのぎょうじゃ)によって開かれた修験道発祥の地、霊峰大嶺山(山上ヶ岳、1,719m)には今も多くの修験者が修行に訪れます。村内には多数の登山コースがあり登山客でにぎわう一方で、毎年山岳遭難事故が数回発生します。地元消防団は山岳救助隊を結成し、警察署からの依頼があれば捜索活動に協力しますが、登山コースの大部分は携帯電話の通信圏外。救助隊の情報共有はトランシーバーを用いた音声情報のみとなっています。そこで、天川村は「シャープ株式会社(シャープ)」などと連携し、2023年度、2024年度総務省「地域デジタル基盤活用推進事業」を活用し、山岳地帯での通信ネットワーク構築や3次元位置情報など利用したアプリケーション(アプリ)などによる山岳救助隊の効率的かつ安全な捜索活動支援の実証事業に取り組んでいます。
一刻を争う中でのトランシーバー頼りは情報共有に難あり
天川村の山岳救助隊は、村消防団本部に所属する7人が中心となり活動しています。しかし、天川村役場総務課の中窪大喜さんは「高齢化による担い手不足のため捜索活動は年々厳しくなっている」と話します。

救助隊は1班3人構成で3班に分かれて、捜索活動を行います。救助隊の隊長を務める猟師の根来一平さんは、山の隅々まで熟知した頼りになる存在です。32歳での隊長就任以降、5年にわたり現場を引っ張ってきました。通常、捜索は朝の8時30分頃に山に入り、夕方まで続けられます。遭難者は、開けた場所ではなく、雨などを避けるために木の下や沢で救援を待つ傾向があるため、ヘリコプターやドローンなどで上空から捜索しても発見できないケースが多く、救助隊の人手に頼らざるを得ない状況です。山岳救助隊が先頭に立ち、山道を踏み分けて進める捜索では、1日8時間歩くこともあります。体力的な負担に加え、遭難者救助は「1分1秒を争う」時間との闘いであるにも関わらず、電波が届かないという山岳地の特殊条件では、情報共有が困難なため、非効率な捜索にならざるをえないという課題を抱えています。

捜索活動中は、トランシーバーによる音声でのやりとりのみであり、共有できる情報は限られています。例えば、捜索中に遺留品らしき物を発見しても、本人のものか否か分からないため、捜索はそのまま続けられ、確認作業が行われるのは、夕方に下山し、捜索本部に持ち帰った後となります。発見物が遭難者の物と確認できても、捜索は翌朝の再開を待つしかありません。
また救助隊自身にも、正確な現在位置の把握や危険位置確認が困難などの課題があり、二次災害の危険性もあります。
これらの課題解決のためシャープは、新しい通信規格による山中での通信可能エリア構築、端末用アプリを連携させた、捜索活動効率化を天川村に提案。県、村、大学、アプリ開発企業などとコンソーシアムを結成し、2023年度と2024年度の地域デジタル基盤活用推進事業(実証事業)で技術や効果の検証に乗り出しました。
通信機材を山に設置し、実証実験を開始 様々な課題を発見
電波が届かず携帯電話が使用できないという捜索活動における最大の課題について、シャープは、2022年に国内で使用可能となった新規格「Wi-Fi HaLow」を使った可搬型中継システムを提案しました。従来のWi-Fiは近距離での高速通信を主眼においたものですが、Wi-Fi HaLowは長距離でも比較的高速なデータ通信が可能です。さらに免許が不要で屋外での使用が可能な上、運用も低コスト。機材は持ち運び可能なサイズであることから、救助隊が持ち運び、「その時」「その場所で」「自由に」通信エリアを構築できる点に着目しました。
しかし、実証実験が開始されると、想定外の困難が立ち塞がりました。シャープの研究開発本部研究員の中谷彩さんが振り返ります。「『見通しがよければ、電波は1km程度飛ぶ』というデータを基に、山中でも数百mごとに中継地点を設けることで、キロメートル単位での通信が可能になるのではないかと考えました。しかし、障害物が多い山中では、思った以上に電波が飛ばないということがわかりました」。そこで、本実証では、電波の到達距離を伸ばすために、高さ5m程度のポールを設置する想定をしましたが、「山中でポールを立てられる場所を探すのが難しい」「山の中に持って入るのは困難だ」などの厳しい声が寄せられました。

加えて、捜索状況や活動指示を分かりやすく共有することを目的に開発したスマートフォンの捜索支援アプリについても、有用性は評価されたものの、操作性の改善を求める声がありました。年配の隊員も多いことから、誰にでも簡単に使えることが導入における第一関門となりました。
2023年度の実証では様々な課題が浮上しましたが、実際に挑戦したことで、Wi-Fi HaLowによる遭難者を捜索する情報共有への期待は高いことを実感でき、次の年度に向けた計画の練り直しに前向きに取り組めました。
通信はドローンで解決! 位置や捜索状況を即座に共有
2024年度は、救助隊からのフィードバックへの対応と、前年度に発見した課題の解決に取り組みました。救助隊からのフィードバックは、「山中に機材を運び、求めている範囲でネットワークを構築するのは困難」という事実でした。そこで、このフィードバックから得られた課題に対して、ドローンにWi-Fi HaLowを搭載し、ドローンがデータを運ぶ手法であれば通信可能範囲を伸長できるのではないかと考え、「株式会社ミラテクドローン」に協力を要請したことが大きな転換点になりました。各班で1人がWi-Fi HaLowの子機、小型PC、バッテリーの3点セットが入ったリュックを背負い、各隊員はアプリがインストールされたスマホを連絡手段に使います。3班に分かれて進む救助隊の上空をWi-Fi HaLowの親機、小型PC、バッテリーを搭載したドローンが巡回。親機と子機がWi-Fi HaLowで接続することにより、救助隊が操作をしなくても自動的にデータの送受信が行われ情報が同期されます。また、ドローンがデータを運んでくれるため、距離が離れている班同士や捜索本部との間で情報が共有でき、通信可能範囲の伸長と共に、ポールが無くなったことにより救助隊の所持機材の大幅な軽量化を実現できました。ドローンは約1時間に1回の頻度で巡回し、遺留品発見などの特別な報告があれば、その班の位置に急行し、最短25分間隔で捜索班が報告したデータを回収し、捜索本部に情報を同期します。


アプリも救助隊のフィードバックを基に、操作性を大幅に改良。操作ボタンを大きくし、操作手順も削減したことで、情報の視認性が向上しました。また、「株式会社Cube Earth(Cube Earth)」の3次元の位置情報を活用する空間ID技術を活用することで、ドローンを介し、正確な現在地の迅速な確認・登録や、移動履歴、画像情報、危険位置情報など捜索状況の即時共有を実現し、二次災害抑制にもつながります。「採算面などを考えるとアプリを一から作り上げるのは企業の取り組みとしては難しいですが、総務省の実証事業という後押しがあったことで、社会的課題の解決に向けて取り組むことができました」とCube Earthの玉置三紀夫さんは話します。

シャープなどによると、1日の捜索時間は最大8時間ほどですが、遺留物などの確認が下山後に限られていたため、日をまたぐことが多いことも課題となっていました。
今回の事業で開発されたドローンを使用した「Wi-Fi HaLowデータ同期システム」とアプリである「高度遭難者捜索システム」を導入すれば、現場から離れることなく遺留品の画像データを本部に送信し、遭難者のものか否かを確認することができるため、山中に散らばっている各班を集め、場所を絞った集中的な捜索に迅速に移行することが可能となります。シャープは、捜索時間を3分の2以下に短縮可能とみており、根来さんも「トランシーバーに頼っている現状に比べれば画期的なシステムです。遺留品が遭難者のものだと確認できれば、30分以内には各班を集めて集中捜索ができるのではないでしょうか」と評価します。

課題はコスト 他地域にも働きかけ横展開を目指す
実装にあたり、残された問題が予算確保です。「導入後にどのようにシステムを維持していくのか。費用対効果でどう折り合いをつけていけるか。コスト面での課題が一番難しい」と天川村の中窪さんは指摘します。そこで、シャープはいくつかの導入形式を提案しています。ひとつは、導入先がドローン、Wi- Fi HaLow通信システム、端末含むアプリを購入・運用する「システム買い切り」型ですが、これには天川村からは「買い切りは費用面、運用面で難しい」との意見がありました。そこで、別案として、捜索時に機材・サービスをレンタルする「レンタルサービス」型を提案。地方公共団体から要請があった際に、シャープからシステム一式と運用者を貸し出す仕組みです。この仕組みであれば地方公共団体の負担は軽減されることから、シャープは、「やろうと思っていたことは全部できた」として、今後、地方公共団体間でのシステムをシェアすることも視野に入れ、全国の山岳遭難事故多発地域の地方公共団体や警察、消防などにも働きかけ、普及拡大につなげていく方針です。